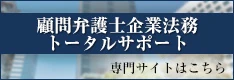【遺産調査・遺産整理/共有物分割】疎遠となっているごきょうだいが亡くなり遺産調査・遺産整理を行うとともに、同居パートナーとの間で遺産不動産の共有物分割を行った事案
相談前
ごきょうだいが亡くなり、内縁のパートナーと一緒に居住していると聞いたことがあるものの、生前にあまり交流がなく、詳しい相続人や財産が不明であるとのことで、ご相談に来られました。
相談後
相続人の範囲、遺産の範囲を調査し、預貯金、生命保険、不動産があることが判明し、不動産については、内縁のパートナーと共有名義であったため、共有物分割調停を申し立て、調停内で任意売却をすることで合意でき、すべての相続財産を換価することができました。
弁護士のコメント
⑴ 遺産調査について
遠縁のご親族が亡くなり、相続人になった場合、他の相続人が誰であるか及びその連絡先、被相続人の遺産の内容が不明であることも多くあります。
このような場合、まずは知っている可能性が高い人物に照会を求める方法があります。本件でも、同居する内縁のパートナーに対し、遺産の内容について照会を求めました。
上記回答と並行し、預貯金であれば、各金融機関に照会、株式であれば「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)、生命保険であれば生命保険協会の「生命保険契約紹介制度」などを利用して遺産調査をすることができます。また、預貯金の調査をする場合には、残高証明書だけではなく、一定期間の取引履歴を取得することで、被相続人の生前の出入金の状況から、新たな財産が判明する可能性もあります。
本件については、内縁のパートナーから得た情報と、別個調査した情報が整合したため、被相続人の遺産の範囲を把握することができました。
⑵ 遺産整理手続について
お子さんがいないごきょうだいが亡くなり、ご両親もすでにお亡くなりになっている場合、ごきょうだい同士が相続人となり、一般に、相続人が多数になる傾向にあります。
相続人が多数いる場合、特段の争いがなくとも、各相続人から書類を回収して各金融機関への書類を提出するなど相続手続が煩雑になります。
当事務所においては、相続人間で紛争がある場合の「遺産分割交渉」と区別して、相続人間で紛争がない場合の手続を行うサービス「遺産整理」も行っています。
相続人間で紛争がなく、手続の代行であるため、「遺産分割交渉」と比較すると安価な費用設定としています。
⑶ 不動産の共有物分割手続
相続に関連して、不動産の共有物分割の手続が必要となるケースは一定数あります。
本件では、被相続人が亡くなったことにより、同居しているパートナーと、被相続人の相続人たちにて共有状態となっており、相続人たちから見ると、全く見ず知らずの方と不動産を共有しており、遺産の換価ができていない状態ということになります。
このような状態を解消するため、民法では、共有者はいつでも共有物分割請求ができることとされています(民法256条1項本文)。
共有物の解消方法としては、不動産を現物で分割する方法(現物分割)、共同で売却して売却代金を分割する方法(換価分割)、共有者のうち一部が取得して代償金を支払う方法(代償分割)があります。
現に居住している共有者がいる場合には、当該共有者が取得を希望することが多いですが、代償金を支払うことができなければ、換価分割の方法に譲歩せざるを得ないケースが多くあります。本件においても、資金繰りの問題から換価分割をすることで合意することができました。
⑷ 名義預金の問題
ある金融機関の預貯金が被相続人名義であっても、実際には、その配偶者が出捐しており、被相続人の所有ではないという主張も一定数見られます(いわゆる名義預金の問題)。
名義預金の問題は、税務署との関係でも問題となりますが、遺産分割をするうえでも問題となります。
本件のように、内縁のパートナーが相手方となる場合には、相続人と内縁のパートナーとの間での預貯金の帰属の問題にもなります。
名義預金の判定は、預金の原資の出捐、預金の管理状況、名義人や関係者の関係、名義人となった経緯等の諸事情を考慮して判断されるものと考えられますが、被相続人に遺産が帰属する側に立証責任があるといえます。
感謝の声

「全てが問題なく、無事終結してくださりありがとうございました感謝しています。」「どんな質問にもめんどくさがらず丁重に説明いただいた。」「先生と言われる方は、偉ぶった言葉を発信する方が多い中全く無い。仕事に置いても満足行くお仕事をしてくれた。」